非有界作用素
|
Read other articles:

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Januari 2023. Peter Rawson TaftPortrait of Peter Rawson TaftLahir(1785-04-14)14 April 1785Uxbridge, MassachusettsMeninggal1 Januari 1867(1867-01-01) (umur 81)Cincinnati, OhioKebangsaan Amerika SerikatPekerjaanPolitikusDikenal atasKakek William Howard TaftS...

本條目存在以下問題,請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法。 此條目需要补充更多来源。 (2018年3月17日)请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而被移除。致使用者:请搜索一下条目的标题(来源搜索:羅生門 (電影) — 网页、新闻、书籍、学术、图像),以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源(判定指引)。 �...
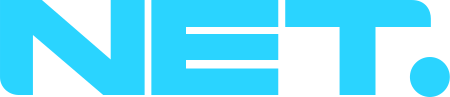
RT 5GenreKomediPemeranCak LontongBeddu ToharRizky InggarDicky DifieFina PhillipeIndra JegelAdjis DoaibuRigen RakelnaDenny ChandraNegara asalIndonesiaBahasa asliBahasa IndonesiaProduksiProduserM. Boniex NurwegaLokasi produksiSound Stage NET., Graha Mitra, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta SelatanDurasi60 menitRumah produksiNET. EntertainmentDistributorNet Visi MediaRilis asliJaringanNET.Format gambarHDTV (1080i 16:9)Format audioDolby Digital 5.1Rilis1 November 2021 (2021-11-01) –...

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (ديسمبر 2022) نادي سامبدوريا هو نادٍ إيطالي محترف لكرة القدم مقره في جنوة، ليغوريا، ويلعب مبارياته في ملعب لويجي فيراريس. تم تشكيل النادي في عام 1946 بعد اندماج سامبيرداري�...

AppingedamBekas munisipalitas / kota BenderaLambang kebesaranNegaraBelandaProvinsiGroningenMunisipalitasEemsdeltaLuas(2006) • Total24,62 km2 (951 sq mi) • Luas daratan23,84 km2 (920 sq mi) • Luas perairan0,78 km2 (30 sq mi)Populasi (1 Januari 2007) • Total12.190 • Kepadatan511/km2 (1,320/sq mi) Sumber: CBS, Statline.Zona waktuUTC+1 (CET) • Musim panas (DST)UTC+2 ...

1924 silent film by Frank Lloyd The Silent WatcherTheatrical release posterDirected byFrank LloydWritten byJ. G. HawksBased onThe Altar on the Hill (story)by Mary Roberts RinehartStarring Glenn Hunter Bessie Love CinematographyNorbert Brodine[1]Edited byEdward M. RoskamProductioncompanies Frank Lloyd Productions[2] First National[3] Distributed byFirst National PicturesRelease date October 5, 1924 (1924-10-05) (U.S.) Running time8 reels[1]Cou...

Lukisan Hebo pada Shan Hai Jing edisi tahun 1597 Hebo (Hanzi: 河伯; harfiah: 'Dewa Sungai') adalah tokoh yang dipuja sebagai dewa penguasa Sungai Kuning. Ia memegang peranan penting dalam sejarah peribadatan di Tiongkok (khususnya Tiongkok bagian utara) serta budaya Tiongkok, baik sastra maupun puisi. Sungai Kuning sendiri merupakan salah satu sumber air utama untuk irigasi bagi lahan pertanian semenjak masa kelahiran peradaban Tiongkok hingga sekarang. Nama Nama Hebo memiliki arti ...

イスラームにおける結婚(イスラームにおけるけっこん)とは、二者の間で行われる法的な契約である。新郎新婦は自身の自由な意思で結婚に同意する。口頭または紙面での規則に従った拘束的な契約は、イスラームの結婚で不可欠だと考えられており、新郎と新婦の権利と責任の概要を示している[1]。イスラームにおける離婚は様々な形をとることができ、個�...

Molineux Informasi stadionNama lengkapMolineux StadiumPemilikWolverhampton Wanderers F.C.OperatorWolverhampton Wanderers F.C.LokasiLokasiWaterloo RoadWolverhampton WV1 4QR InggrisKoordinat52°35′25″N 2°07′49″W / 52.59028°N 2.13028°W / 52.59028; -2.13028Koordinat: 52°35′25″N 2°07′49″W / 52.59028°N 2.13028°W / 52.59028; -2.13028KonstruksiDibuat1889Dibuka1889Direnovasi1991–1993Data teknisPermukaanRumputKapasitas27,828U...

Romanian politician (1960–2019) Sorin FrunzăverdeSorin Frunzăverde in February 2007Member of the European ParliamentIn office2007–2009Minister of National DefenseIn office25 October 2006 – 5 April 2007Prime MinisterCălin Popescu-TăriceanuPreceded byCorneliu Dobrițoiu (acting)Succeeded byTeodor MeleșcanuIn office13 March 2000 – 28 December 2000Prime MinisterMugur IsărescuPreceded byConstantin Dudu IonescuSucceeded byIoan Mircea PașcuMinister of TourismIn offic...

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)出典検索?: コルク – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年4月) コルクを打ち抜いて作った瓶の栓 コルク(木栓、�...

Sport This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Beach rugby – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (July 2011) (Learn how and when to remove this message) Beach Rugby match Beach rugby is a sport that is based on rugby union. Currently there is not a centralized regulation of the sport as in beach soccer or beach...

Salah satu contoh manuskrip Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah adalah sebuah karya sastra Melayu yang termasyhur dan mengisahkan Hang Tuah. Dalam zaman kemakmuran Kesultanan Malaka, Hang Tuah adalah seorang laksamana yang amat termasyhur. Ia berasal dari kalangan rendah, dan dilahirkan dalam sebuah gubug reyot. Tetapi karena keberaniannya, ia amat dikasihi dan akhirnya pangkatnya semakin naik. Maka jadilah ia seorang duta dan mewakili negeranya dalam segala hal. Hang Tuah memiliki beberapa ...

「俄亥俄」重定向至此。关于其他用法,请见「俄亥俄 (消歧义)」。 俄亥俄州 美國联邦州State of Ohio 州旗州徽綽號:七葉果之州地图中高亮部分为俄亥俄州坐标:38°27'N-41°58'N, 80°32'W-84°49'W国家 美國加入聯邦1803年3月1日,在1953年8月7日追溯頒定(第17个加入联邦)首府哥倫布(及最大城市)政府 • 州长(英语:List of Governors of {{{Name}}}]]) •&...

Ця стаття потребує додаткових посилань на джерела для поліпшення її перевірності. Будь ласка, допоможіть удосконалити цю статтю, додавши посилання на надійні (авторитетні) джерела. Зверніться на сторінку обговорення за поясненнями та допоможіть виправити недоліки. Мат...

Pour les articles homonymes, voir Adamson. Donald AdamsonDonald Adamson en 2014.BiographieNaissance 30 mars 1939Culcheth, AngleterreDécès 18 janvier 2024 (à 84 ans)Polperro, AngleterreNationalité britanniqueActivités Biographe, écrivain, critique littéraire, professeur d'université, historien de la littérature, traducteur, spécialiste de littérature françaisePère Donald Adamson (d)Mère Hannah Mary Booth (d)Conjoint Helen Griffiths (d) (de 1966 à 2024)Enfants Richard Adams...

Centre des sports de glisse de WhistlerGénéralitésAdresse CanadaConstruction et ouvertureDébut de construction 1er juin 2005Ouverture 19 novembre 2007Architecte Stantec Architecture LimitedCoût de construction 105 millions de dollars canadiensUtilisationPropriétaire VANOC (2005-2010) Whistler 2010 Sports Legacies (2010-)Administration VANOC (2005-2010) Whistler 2010 Sports Legacies (2010-)ÉquipementCapacité 12 000Dimensions Bobsleigh/ Skeleton: 1 450 m Luge - homm...
Form of society Leisure society redirects here. For the band, see The Leisure Society. Part of a series onAutomation Automation in general Banking Building Home Highway system Laboratory Library Broadcast Mix Pool cleaner Pop music Reasoning Semi-automation Telephone Attendant Switchboard Teller machine Vehicular Vending machine Robotics and robots Domestic Vacuum cleaner Roomba Lawn mower Guided vehicle Industrial Paint ODD Impact of automation Manumation OOL Bias Self-driving cars Technolog...

1820 Connecticut gubernatorial election ← 1819 April 13, 1820 1821 → Nominee Oliver Wolcott Jr. Nathan Smith Timothy Pitkin Party Democratic-Republican Federalist Federalist Popular vote 15,738 2,659 1,140 Percentage 76.14% 12.86% 5.52% County resultsWolcott: 60–70% 70–80% 80–90% >90% Governor before election Oliver Wolcott Jr. Dem...

وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة الاقتصاد والتخطيط (السعودية)وزارة الاقتصاد والتخطيط تفاصيل الوكالة الحكومية البلد السعودية الاسم الكامل وزارة الاقتصاد والتخطيط تأسست 1390 هـ 1970 المركز الرياض، السعودية الإدارة منصب المدير وزير الاقتصاد والتخطيط [لغات أخرى]&...






































